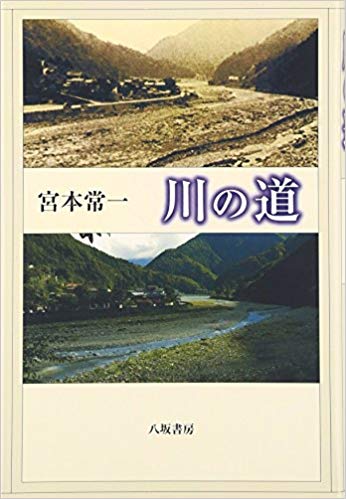1975年に、民俗学者「宮本常一」によって書かれた本、『川の道』を読み終わりました。
図書館で借りて自宅で読みました。
読んだのは2009年に刊行された新版です。
「旅の民俗と歴史」シリーズの9冊目となる本で、川がまだ交通手段として使われていた昔の、日本人と川の関係について書かれています。
内容
川は日本人にどのようなかかわりあいをもっていたか。田畑をうるおし、飲料水を供給し、交通路になり、また魚介をわれわれに提供し、海岸地方の文化が山奥深くへ、山間の物資が海岸地方へ……川は漁労や治水にのみならず、人や物資交流の道として、山と海を結ぶ重要な役割を果していた。
日本の主な河川37をとりあげて、それらの川の果たしてきた人間とのかかわりあいの歴史を綴る。
(八坂書房ウェブサイトより)
感想など
川は道であった。
巨大なダムが流れをせき止め、川筋に鉄の塊が往来する現代日本において、川が道であったことを実感することは難しい。
しかし人力と自然の力だけだった明治前は、川は物流に深く関係した。
人力で道を作り、そこを徒歩や牛馬で往来するのは多大な労力がかかる。
しかし川を使えば道の整備はほとんど必要無くなり、水深によるが重い物や大量の物を一気に運ぶことも出来る。
言ってみれば、川とは自然に出来た街道である。
ダムや鉄道が出来る前は、川を使って多くの物が上流と下流を行き来した。
上流からは、農産物、丸太や木炭などの林産物、重くて嵩張る素材が多く流れた。
対して下流からは、塩、各種の道具、肥料(金肥や干鰯)など、海や街で作られた軽くて価値のあるものが運ばれた。
川はもちろん上流から下流へ流れる。
では下流から上流へ行くにはどうすれば良いか?
今ではあまり想像できないが、何と「曳綱」で曳いて上っていたようだ。
そのため下へ流れるより、上に上っていくほうが何倍も時間と労力がかかり、川男たちは川筋の町で宿泊しながら上流へ戻っていたようだ。
物流を担う川男たちは運んだ量によって得られる金が変わるが、その時代においては比較的稼げる仕事だったようだ。
筑豊では石炭の物流を川船が担っていた時代もあったが、そこで働く男たちはなかなか粗暴で、現代で言えばトラック運転手をイメージすると合うかもしれない。
そう言えばこの筑豊の石炭であるが、中世から燃料として使われていたようで、江戸時代には瀬戸内海沿岸の塩田地帯で製塩燃料として使われるようになったらしい。
元塩田地帯で生まれ育った身としては、なかなか興味深い記述だ。
塩づくりには大量の燃料が必要になるが、郷土の塩づくりの燃料についての研究の一助になりそうな事実である。
最後に、印象に残ったのは冒頭にあった以下の文章。
川筋を伝って文化が奥地へはいってゆくというのは、そこを人が通って奥地へはいっていったと言っていい。
いろいろの困難を克服しながら、人びとは自分たちの夢を拡大し、また可能性の限界をためしてみるために、その生活領域を拡大していった。
もともと人間はより住み易い地を求めていったものが多いのであろうが、それとは別に、そこに人が住めるということになると、どのように条件が悪くてもそれを克服してそこに住むことを辞さなかった。
世界のすみずみにまで人が住んだのはそのためであった。
日本についてみても、どんな山の奥にも、地の果てにも、また沖の小島にも人は住みついている。
p12
「こんな山奥になぜ人々が住んでいるのか」ということを考える時、川と物流を必ず考慮せねばならない。
物流が良く、広くて使いやすい土地で、経済的なものを産出出来るなら、自ずと人が住んでいく…
と思いきや、日本を隅々まで歩いた宮本常一先生が言うには、人がそこに住む理由はそれだけじゃないらしい。
冒険心こそが、辺鄙な場所にまで人類を運んだ。
手付かずの大自然を前に、挑んでいった先人たちの想いを、私は知りたい。