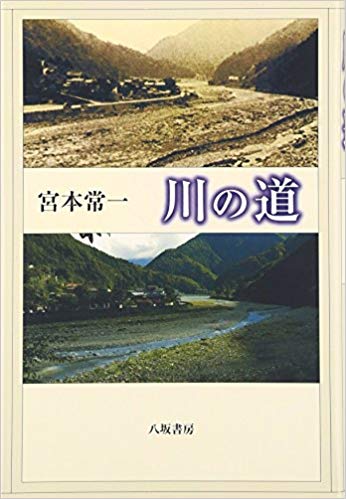あらすじと目次
本書は、生活学の先駆者として生涯を貫いた著者最晩年の貴重な話――
「塩の道」「日本人の食べもの」「暮らしの形と美」の3点を収録したもので、日本人の生きる姿を庶民の中に求めて村から村へと歩きつづけた著者の厖大なる見聞と体験が中心となっている。
日本文化の基層にあるものは一色でなく、いくつかの系譜を異にするものの複合と重なりであるという独自の史観が随所に読みとれ、宮本民俗学の体系を知る格好の手引書といえよう。
- 1 塩の道
1.塩は神に祭られた例がない
2.製塩法とその器具の移り変わり
3.塩の生産量の増加に伴う暮らしの変化
4.塩の道を歩いた牛の話
5.塩を通して見られる生活の知恵
6.塩の通る道は先に通ずる重要な道 - 2 日本人と食べもの
1.民衆の手から手へ広がっていった作物
2.北方の文化を見直してみよう
3.稲作技術の広がり方
4.人間は食うためにだけ働いているのではない
5.食糧を自給するためのいろいろなくふう - 3 暮らしの形と美
1.環境に適応する生活のためのデザイン
2.農具の使い方にみる日本人の性格
3.直線を巧みに利用した家の建て方
4.畳の発明で座る生活に
5.軟質文化が日本人を器用にした
6.生活を守る強さをもつ美
感想など
塩の生産と流通の歴史
人類にとって、塩は生きるために必要不可欠なものである。
しかし塩の歴史や民俗学の研究は(かつては)あまりなされておらず、あったとしても専売公社が関わるもので、一般向けの書物は少ないようだ。
そういう意味で、この本は価値があると思う。
塩の製造方法にも歴史があり、技術や流通の変化によって主たる方法は以下のように変遷している。
- 土器で海水を煮る、藻塩を焼く
- 古式入浜という、干潟のような場所で潮の満ち引きを利用して、塩分の濃い鹹水を得る方法。
- 古式入浜を石垣などで整備した、入浜塩田。
- 流下式枝条下、ホウキ状の構造物に海水をかけて蒸発しやすくする。
- イオン交換膜法、電気と膜によって海水から塩化ナトリウムを抽出する。
鹹水を煮る釜はかつては土器だったが、石窯と鉄釜になっていった。
鉄釜は生産効率が良いが、赤錆が混ざって白い塩にはならない。
良質の塩作りには、石窯(片麻岩)を使った。
釜の分布も、良質な鉄の取れやすさや石の取れやすさで変わっていた。
山の人間は塩を得るため、ほぼ必ず何らかの方法で海と関わっていた。
最初期は、川に木を流し、河口で回収して薪にして、塩を作って持ち帰った。
その後、多めに木を流して海岸の人に作ってもらった。流した木のいくらかは手間賃として渡していた。
江戸時代、瀬戸内海の塩が全国各地に船で流通するようになった。山の人が塩を買うための金は、薪や灰で賄った。
塩の陸上運送はもっぱら牛を使っていた。
山に塩を運び、山の生産物を平地や海に降ろしていたりしていた。
牛や馬で運べないところは、人の背(ボッカ)で運んだ。
荷の単価を上げるため、塩漬けした魚も運んだ。
塩は、明治38年の専売制が始まるまで、上記のように生産や流通は人々の需給に応じて有機的に変わっていった。
塩の帳面の例に、「阿波斎田塩」「周防平生塩」があったが、他にも「阿波平生斎田塩」「周防平生斎田塩」というものもあった。
意味の詳細は不明。
もう少し調べてみたい。
日本人と食べ物
食べ物の移入とその様子を考える。
サツマイモ、トウモロコシ、カボチャ、ジャガイモ、サトウキビは中世・近世に導入された重要作物である。
サツマイモは大名や代官が尽力して広めたなどの記録も残っているが、同じくエネルギー源として重要なトウモロコシが広がっていく様子はまちまちである。
旅行者が故郷に持ち帰ったなど、大々的に導入されたことは少ない。
かつてはクリを始めとする果殻類も大いに食べられ、その木も保護されていたようだ。
しかし、クリは線路の枕木とするため、明治以降は全国的に伐採されてかなり少なくなった。
サツマイモを生産していた場所(西日本の低地)は飢饉にも耐え、生活や経済が安定していった。
東日本は飢饉があったので、江戸時代ではなかなか人口が増えていかなかった。
…とまあ、雑多的に興味深い箇所を抽出してみたが、いかがなものだろう。
本書の三篇は宮本先生が晩年に行った講演を元にした本で、先生ならではの仮説も多く載っている。
先生よりも遥かに知識の少ない自分から見れば首をかしげるような仮説もあるが、それを間違いじゃないかと判断するのは、先生レベルの膨大な情報を得てからである。
今後も民俗学の本を読んで、先生の仮説に共感出来るようになったり、郷土史の研究の一助にしていきたいと思う。